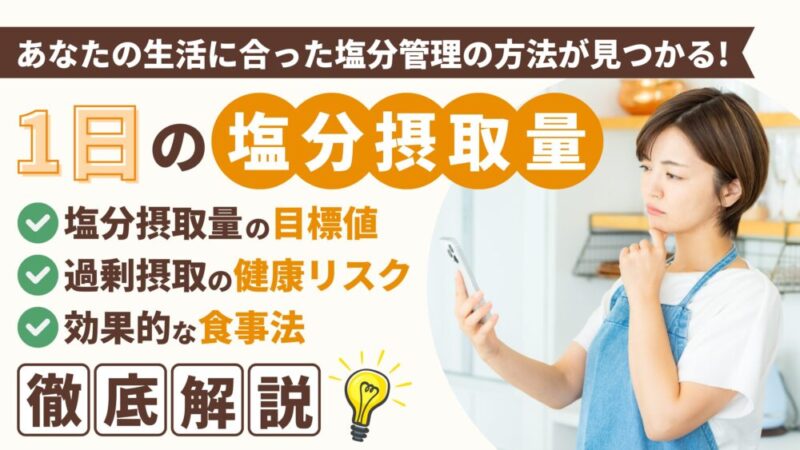
健康的な生活を実現するため、塩分の摂取量や効果的な減塩方法について悩む人は多くいます。この記事では、1日の塩分摂取量の目標値や過剰摂取の健康リスク、効果的な食事法などを解説します。記事を読めば、あなたの生活に合った塩分管理の方法が見つかり、健康的な食生活の実現が可能です。
1日の塩分摂取量の目標値

1日の塩分摂取量の目標値は、健康維持のための重要な指標です。1日の塩分摂取量の目標値について以下を解説します。
- 健康な成人の目標値
- 持病がある場合の目標値
適切な摂取量は、年齢や性別、健康状態によって異なります。塩分の過剰摂取は高血圧や心臓病などのリスクを高めるため、適切な摂取量を守りましょう。
健康な成人の目標値
健康な成人の1日の塩分摂取量の目標値は、男性が7.5g未満、女性が6.5g未満です。塩分摂取量の目標値は、健康維持と生活習慣病予防のために、厚生労働省が定めた基準です。世界保健機関(WHO)はさらに厳しい基準を設けており、5g未満/日を推奨しています。
年齢や性別に関わらず、できるだけ減塩を心がけると健康的な食生活につながります。1日2g以上の減塩で血圧抑制効果が期待できるため、少しずつでも塩分摂取量を減らす努力をしましょう。気になる点は医師に相談し、健康状態や生活習慣に応じて調整してください。
持病がある場合の目標値
持病がある場合は、健康状態に応じて塩分摂取量の目標値が異なります。それぞれの目標値は、以下のとおりです。
- 高血圧患者:6g未満/日
- 慢性腎臓病患者:6g未満/日
- 心不全患者:6g未満/日
- 脳卒中患者:6g未満/日
- 妊娠高血圧症候群患者:6g未満/日
- 糖尿病患者:7g未満/日
- 肝硬変患者:7~8g/日
- 骨粗しょう症患者:8g未満/日
目標値は、各疾患の特性や塩分が与える影響を考慮して設定されています。医師や栄養士と相談し、自分に適した塩分摂取量を守りましょう。減塩を心がけると徐々に味覚が変化し、薄味でもおいしく感じられます。
日本人の1日の塩分摂取量

日本人の1日の塩分摂取量には、男女差や年齢差、地域差があります。日本人の1日の塩分摂取量について、以下を解説します。
- 平均的な塩分摂取量
- 地域別の塩分摂取量
健康意識の高まりで摂取量は減少傾向にありますが、国際的にはまだ高水準です。健康維持のためには、塩分摂取量を意識的に減らす取り組みが必要です。

汗いっぱいかいた日は、スポドリや塩分入りタブレットで塩分補給してもいいんでしょ?

そうですね。夏でも塩分は1日5g未満が目安ですが、炎天下でたくさん汗をかいた日は、失われた分を0.5〜1gだけ追加すると安心です。スポーツドリンクや塩分タブレットを使うときは、食事の塩分と合わせて5gを超えないように気をつけましょう。カリウムやマグネシウムも一緒にとると、熱中症予防に効果的ですよ!
炎天下での運動・屋外作業と塩分補給の目安
| 運動・作業時間 | 推定発汗量 | 失われる塩分量 | 補給目安(スポドリ) | 補給目安(塩分タブレット) |
|---|---|---|---|---|
| 30分 | 0.3〜0.5L | 0.6〜1.5g | 200〜300ml | 1粒程度(0.1〜0.3g) |
| 1時間 | 0.5〜1L | 1〜3g | 500ml | 1〜2粒(0.2〜0.6g) |
| 2時間 | 1〜2L | 2〜6g | 500〜1000ml | 2〜3粒(0.4〜0.9g) |
| 3時間 | 1.5〜3L | 3〜9g | 1〜1.5L | 3〜4粒(0.6〜1.2g) |
💡補足
- スポーツドリンクは500mlあたり塩分0.5〜1g(商品差あり)
- 塩分タブレットは1粒0.1〜0.3gが目安
- 食事の塩分と合計で1日5g未満に収めるのが理想
- 高血圧や腎臓疾患がある方は、医師に相談してから調整
平均的な塩分摂取量
日本人の平均的な塩分摂取量は1日約10gで、世界保健機関(WHO)の推奨量5g/日を大幅に超えています。男性の平均摂取量は約11g、女性は約9gです。年齢が上がるにつれて摂取量が増加する傾向があります。
厚生労働省が定めた目標値(男性7.5g未満、女性6.5g未満)と比較しても、現状の摂取量は高すぎる状況です。
地域別の塩分摂取量
地域の食文化や気候は、塩分摂取量に大きな影響を与えています。東北地方が最も高く、1日あたり約11~12gの塩分を摂取しています。最も低いのは沖縄県で、1日あたり約8~9gです。北海道や東北地方は、寒冷な気候や塩蔵食品の消費の多さから、塩分摂取量が多くなっています。
寒冷地域では、保存食として塩分の多い食品が好まれます。西日本は、東日本に比べて全体的に摂取量が少ない傾向です。都市部では外食や加工食品の利用が多く、家庭での調理機会が少ないため、塩分摂取量が多くなっています。住む地域の特徴を踏まえて、適切な塩分摂取量を意識しましょう。
塩分過剰摂取の健康リスク

塩分の過剰摂取が及ぼす健康リスクは、以下のとおりです。
- 高血圧の原因になる
- 心疾患や脳卒中のリスクが高まる
- 腎機能低下の原因になる
塩分摂取の欲求は次の3つの要因から引き起こされ、それにより弊害をもたらします。
1. 味覚の慣れ
塩分が多い食事に慣れると、舌がその強い塩味を基準として感じ、通常の塩分量の料理では物足りなさを感じるようになります。
2. 快感をもたらす要素
塩味は食材の旨味を引き出すため、満足感や食べる楽しさを増します。この満足感が「もっと食べたい」という欲求を引き起こし食べ過ぎの原因にもなります。
3. 生理的な要因
体がナトリウムを必要とするときに塩味を欲することがあります。ただし、これは体が塩分不足である場合に限ります。塩分だけでなく、カリウムやマグネシウムなどの電解質も含む飲料を摂り、必要以上に塩分摂取をしないようにしましょう。
高血圧の原因になる
高血圧の原因の1つが、塩分の過剰摂取です。塩分を摂りすぎると、ナトリウム濃度を調整する体の仕組みが働き、体内の水分量が増加します。血液量が増えて血圧が上昇すると、血管への負担が大きくなり、高血圧の状態が続きます。血管壁の硬化が促進され、交感神経系が活性化するのも特徴です。
血管内皮機能の低下やレニン-アンジオテンシン系の活性化なども、高血圧につながります。高血圧は自覚症状がほとんどなく、気付かないうちに進行します。早期発見のためには、定期的な血圧測定と適切な塩分管理が重要です。
心疾患や脳卒中のリスクが高まる
高血圧が続くと、心臓や血管に大きな負担がかかり、心疾患や脳卒中のリスクが高まります。心疾患や脳卒中は、動脈硬化の進行や血管の損傷が原因です。血管壁への負担が増えると、血管が傷つきやすくなります。心臓に過度な負担がかかれば、心肥大や心不全の危険性が上がります。
脳血管が破れやすくなると脳卒中のリスクが高まるため、注意が必要です。冠動脈疾患や狭心症などの心臓病のリスクも増加します。血栓ができやすくなれば、心筋梗塞や脳梗塞のリスクも上昇します。血管の弾力性の低下により、循環器系の障害のリスクも高まるため注意しましょう。
腎機能低下の原因になる
塩分の過剰摂取は、腎機能の低下につながります。塩分の摂りすぎが腎機能に悪影響を与える理由は、以下のとおりです。
- 高血圧による負担増加
- ろ過機能の低下
- 血管の硬化
- 炎症の促進
過剰な塩分摂取が続くと、腎臓に直接的なダメージを与え、むくみの悪化や腎臓結石のリスク増加につながります。尿中カルシウム排出量が増加し、腎臓の線維化が進行します。腎臓は、体内の老廃物を排出する重要な役割を担っているため、機能の低下は大きな問題です。腎臓への悪影響が重なると、慢性腎臓病の進行を招きます。
塩分を多く含む加工食品と外食メニュー
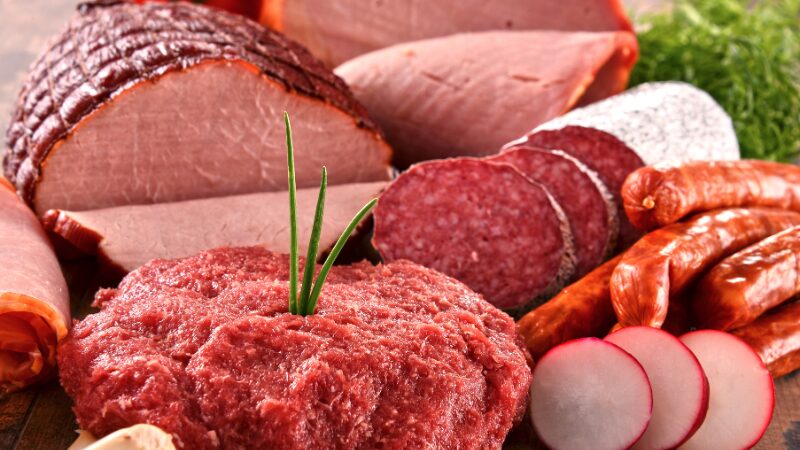
加工食品と外食メニューには予想以上に塩分が含まれているため、注意が必要です。頻繁に摂取すると、知らないうちに塩分の摂りすぎにつながります。塩分の多い食品を把握し、摂取量を意識的に調整しましょう。
加工食品
塩分を多く含む加工食品は、以下のとおりです。
- インスタントラーメン
- カップスープ
- レトルトカレー
- ハム
- ソーセージ
- 漬物
加工食品は便利で手軽に食べられるため、つい摂りすぎてしまいます。加工食品を選ぶ際は、パッケージの栄養成分表示を確認し、塩分量の少ないものを選びましょう。加工食品に頼りすぎず、新鮮な野菜や果物、魚などの自然食品を中心とした食生活を心がけてください。
外食メニュー
外食メニューは調理過程で多くの塩分が加えられているため、注意が必要です。塩分が多い外食メニューは、以下のとおりです。
- ラーメン
- 丼物
- ハンバーガー
- ピザ
- フライドポテト
- ギョーザ
- 唐揚げ
- カレーライス
- 中華料理
- 焼き鳥(タレ)
外食を完全に避けるのは現実的ではないため、メニューの選び方や食べ方を工夫しましょう。うどんやそばはつゆを残し、寿司はしょうゆを控えめにすると効果的です。サラダはドレッシングの量に注意し、スープは具だけを食べると塩分を抑えられます。
1日の塩分摂取量を管理する方法

1日の塩分摂取量を管理する方法は、以下のとおりです。
- 塩分を計測する
- 食品のラベルを見る
- 食事内容を記録する
適切な管理方法を知り、日々実践すると塩分の過剰摂取を防げます。
塩分を計測する
塩分を計測すると、正確な塩分摂取量の把握が可能です。家庭用の塩分計を使えば、調理した料理の塩分濃度を簡単に測定できます。汁物の塩分を測る際は、塩分濃度計が便利です。調味料を使う際は計量スプーンを活用しましょう。大さじ1杯のしょうゆには約2.5gの塩分が含まれています。
食品成分表やスマートフォンアプリを使えば、食材や料理の塩分含有量を確認できます。ツールを上手に活用すると、塩分摂取量の効果的な管理が可能です。
食品のラベルを見る
食品のラベルを見て栄養成分表示を確認すると、食品に含まれる塩分量を把握できます。1食分あたりの塩分量や100gあたりの塩分量を確認しましょう。原材料表示で塩分を含む成分を確認するのも効果的です。「減塩」や「低塩」の表示がある商品は、通常の商品と比べて塩分が少ない傾向にあります。
複数の商品の塩分量を比較し、より塩分の少ない商品を選びましょう。同じ種類の食品でも、ブランドによって塩分量が異なります。調味料は少量でも塩分を多く含むため、使用量に注意が必要です。外食の際は、メニューの栄養成分表示を確認しましょう。
飲食店では栄養成分表示が義務付けられているため、塩分量を確認してから注文できます。栄養成分表示を見る習慣を付けると、日々の塩分摂取量の正確な把握が可能です。
食事内容を記録する
食事内容を記録すると、自分の食生活を客観的に把握できます。食事の写真を撮影し、手帳やノートに記録を残しましょう。スマートフォンアプリやオンラインサービスの活用もおすすめです。外食時のメニューや調味料の使用量も忘れずに記録しましょう。毎日の塩分摂取量を計算し、グラフ化して傾向を把握すると効果的です。
食事記録を定期的に振り返り、改善点を見つけましょう。食事記録と体調の変化を関連付けて分析すると、自分の体に合った塩分摂取量を把握できます。家族や友人と記録を共有し、サポートし合うのも効果的です。医療専門家に食事記録を見せてアドバイスを受ければ、より適切な塩分管理ができます。
1日の塩分摂取量を減らすポイント

1日の塩分摂取量を減らすポイントは、以下のとおりです。
- 薄味の食事を心がける
- 減塩調味料を使用する
- だしや香辛料を活用する
- 加工食品や外食を減らす
毎日の食事を少しずつ工夫し、無理なく塩分摂取量を減らしましょう。
薄味の食事を心がける
薄味の食事を心がけると、1日の塩分摂取量を効果的に減らせます。野菜や果物の甘みを生かし、食材本来の味を楽しみましょう。酢やかんきつ類の酸味を活用するのも効果的です。調味料は計量して使用し、徐々に薄味に慣れましょう。調理法を工夫して素材の味を引き出すと、塩分に頼らなくてもおいしい料理を作れます。
塩分の強い食材は量を控えめにするのもポイントです。家族みんなで意識して取り組めば、効果的に塩分摂取量を減らせます。

「へえ〜!酸っぱいものを入れると、なんで薄味でもおいしく感じるの?

それはね、酢や柑橘類を使うと、酸味が食材の味を引き締め、旨味や香りを引き立てるからです。さらに、酸味には唾液の分泌をうながす働きがあります。唾液は食べ物の成分を溶かし、味蕾(みらい)は水に溶けた成分にしか反応しないため、成分が味蕾に届きやすくなります。こうして薄味でも味を十分に感じられ、満足できるのです!
減塩調味料を使用する
減塩調味料を使用すると、塩分を抑えつつ料理のおいしさを保てます。減塩調味料は、塩の一部をカリウムやマグネシウムで代替した製品です。塩分〇%カットの表示がある調味料を探しましょう。減塩しょうゆは刺身や冷ややっこなどの生食に、減塩みそは煮物やみそ汁に使用すると効果的です。
通常の調味料と併用し、徐々に慣れていきましょう。最初は通常の調味料と減塩調味料を半々で使い、少しずつ減塩調味料の割合を増やすのがおすすめです。減塩調味料を選ぶ際は、栄養成分表示をよく確認してください。塩分量だけでなく、カリウムやマグネシウムの含有量も確認しましょう。
料理の下味に減塩調味料を使うと、より効果的に塩分を減らせます。減塩調味料と香辛料を組み合わせて、味に変化をつけるのもおすすめです。
だしや香辛料を活用する

だしや香辛料を活用すれば、健康的でおいしい食事を楽しめます。香辛料やハーブ、香味野菜を使用すると、食事に風味が加わります。食材を上手に使い、減塩しつつ味わい深い料理を作りましょう。酢やしょうゆで味に深みを出したり、ごまやナッツ類でコクを出したりするのも効果的です。
みそやしょうゆは塩分が多いため、薄めて使用しましょう。香ばしさを出すために、ごま油を使用するのもおすすめです。魚や肉に下味をつけて調理すると、減塩しながらおいしく食べられます。
加工食品や外食を減らす
加工食品や外食を減らすと、塩分摂取量を効果的に調整できます。自炊をする機会を増やし、使用する食材や調味料をコントロールしましょう。新鮮な食材で素材本来の味を引き出すと、塩分に頼らずにおいしい料理を作れます。加工食品を使用する場合は、減塩タイプを選びましょう。
加工食品の代わりに手作りのおかずを選べば、添加物や過剰な塩分を避けられます。冷凍食品やインスタント食品の使用は控え、生鮮食品を選択しましょう。弁当を持参し、外食を減らすのもおすすめです。外食の際は栄養成分表示を確認し、塩分控えめのメニューを選択してください。
まとめ

健康維持のためには、塩分摂取量の管理が欠かせません。自分に合った目標値を把握し、日々の食事で意識しましょう。日本人の平均塩分摂取量は目標値を上回っているため、塩分を意識的に減らす取り組みが必要です。塩分の摂りすぎは、高血圧や心臓病などの健康問題につながります。
加工食品や外食は塩分が多く含まれているため、注意が必要です。塩分の計測や食品表示の確認を習慣化し、自分の塩分摂取量を把握しましょう。だしや香辛料を活用すると、塩分が少なくてもおいしい食事を楽しめます。少しずつでも塩分を減らす工夫を続けると、健康的な食生活を実現できます。
» 食生活の重要性と年齢別の改善方法を解説