
野菜は健康維持に欠かせませんが、「野菜ならたくさん食べても大丈夫」と考える人もいます。積極的な野菜の摂取は大切ですが、野菜の食べ過ぎにはデメリットもあるため注意が必要です。この記事では、野菜の適切な摂取量や食べ過ぎによるデメリット、正しい野菜の取り入れ方について解説します。
記事を読めば、体質や生活スタイルに合った野菜の摂取方法がわかり、健康的な食生活を送れます。
» 食生活の重要性と年齢別の改善方法を解説
厚生労働省が推奨する野菜の摂取量は1日350g
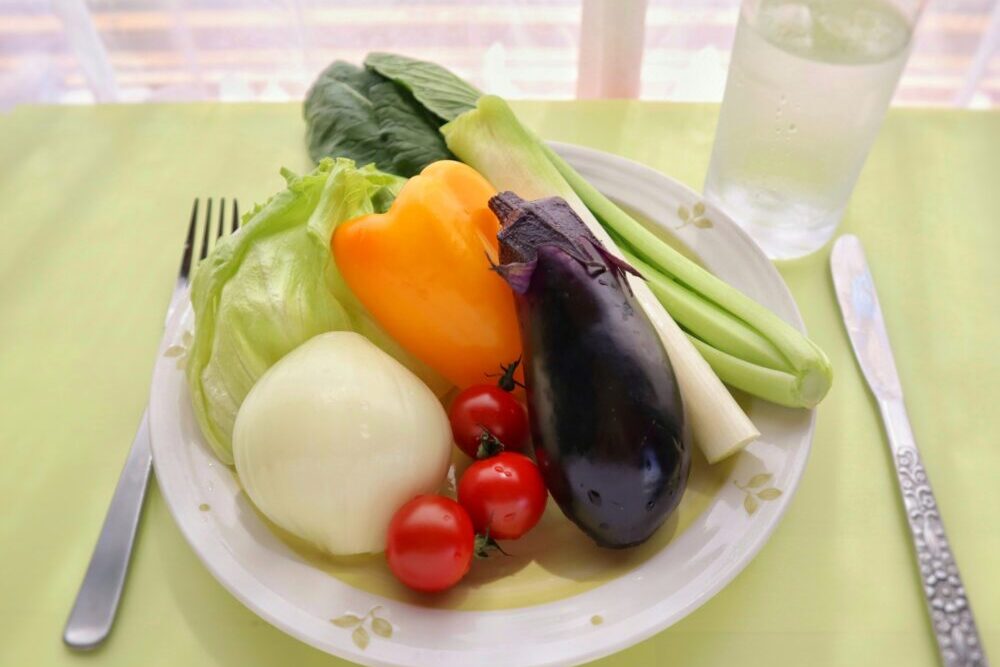
厚生労働省は1日の野菜摂取量を350g以上と定めていますが、日本人の平均野菜摂取量は約280gにとどまっています。野菜摂取量の目安は、以下のとおりです。
- 生野菜なら両手5杯分
- 茹で野菜なら片手5杯分
野菜摂取量350gの内訳は、緑黄色野菜が120g以上、その他の野菜が230g以上です。
» 野菜摂取目標量350gを達成する方法を伝授
野菜を食べ過ぎるデメリット
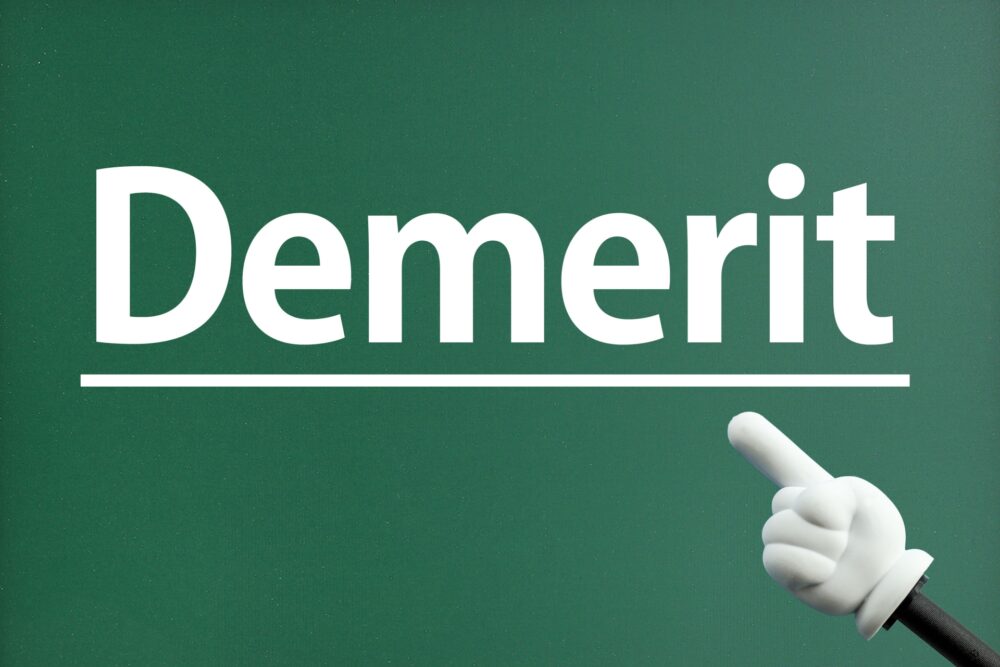
野菜を食べ過ぎるデメリットは、以下のとおりです。
- 下痢や便秘になる
- 胃痛や吐き気の原因になる
- たんぱく質が不足する
- 重要なビタミンやミネラルが不足する
- 太る
- 酵素の働きを妨げる
- アレルギー反応のリスクがある
下痢や便秘になる
食物繊維をとれば便秘が治る」――そう思っていませんか?
実は、水分が不足した状態で食物繊維を多くとると、かえって便秘が悪化することもあるんです。野菜を食べ過ぎると食物繊維の過剰摂取になり、腸内環境が乱れ、下痢や便秘の原因につながる場合があります。食物繊維には水溶性と不溶性があり、どちらもバランス良く取ることが大切です。
🥬 野菜に含まれる食物繊維の種類
| 野菜の名前 | 主な食物繊維の種類 | 特徴・便秘への効果 |
|---|---|---|
| ごぼう | 不溶性 | 腸を刺激して便通をうながすが、食べすぎはお腹が張ることも。 |
| キャベツ | 不溶性 | 便のかさを増やして排便を促す。加熱するとやわらかく食べやすい。 |
| にんじん | 不溶性(一部水溶性) | 適度な繊維で腸の動きを助ける。加熱しても繊維が残る。 |
| ほうれん草 | 不溶性 | ビタミン豊富で、腸のぜん動運動をサポート。 |
| かぼちゃ | 不溶性+水溶性 | 便をやわらかくし、排出しやすくなる。バランスのよい食材。 |
| モロヘイヤ | 水溶性 | ネバネバ成分が便を包み、やわらかくして出しやすくする。 |
| オクラ | 水溶性 | 粘り成分が腸内をなめらかにし、便のすべりをよくする。 |
| なめこ | 水溶性 | ぬめりが腸内で潤滑油のような働きをし、排便を助ける。 |
| 大根(生) | 水溶性(おろし汁に多い) | 消化を助け、便をやわらかくする効果がある。 |
| トマト | 水溶性 | 水分と食物繊維の両方を含み、自然な排便をうながす。 |
生野菜の食べ過ぎは、便が硬くなって出にくくなる一因です。キャベツやブロッコリーには消化されにくい糖が含まれるため、食べすぎるとお腹にガスがたまり、不快感が出る場合があります。野菜の種類によっては、体質に合わず消化不良を引き起こす場合がありますが、多くの場合は一時的な症状です。
胃痛や吐き気の原因になる
生野菜を大量に摂取した場合、胃痛や吐き気を引き起こす可能性があります。生野菜には食物繊維が豊富に含まれているため、一度に大量に摂取すると胃腸に負担がかかります。普段から野菜をあまり食べない人は、生野菜の大量摂取に注意してください。野菜の食べ過ぎによって現れる症状は、以下のとおりです。
- 腹部膨満感
- 胃粘膜への刺激
- 農薬や添加物への過敏反応
特定の野菜に含まれるサリチル酸塩が原因で、胃の炎症を引き起こす人もいます。野菜の種類によっては、FODMAP(※1)と呼ばれる特定の炭水化物が過敏症を引き起こし、胃腸症状の原因になります。細菌感染で胃痛や吐き気などの症状が現れる場合があるため、十分に洗浄していない野菜を食べる際には注意が必要です。
※1 FODMAPとは、腸で吸収されにくい発酵性の糖質の総称です。過敏な人が取ると、ガスや腹痛、下痢などを引き起こす場合があります。
たんぱく質が不足する

野菜だけを多く食べて他の食品を制限すると、体に必要なたんぱく質が不足するおそれがあります。たんぱく質は筋肉や臓器、皮膚、髪の毛を作るために欠かせません。成人の場合、体重1kg当たり約0.8gのたんぱく質が必要です。たんぱく質不足により生じる問題は、以下のとおりです。
- 筋力の低下
- 疲れやすさ
- 免疫力の低下
- 肌や髪の状態悪化
- むくみ
菜食主義の人は、豆腐や納豆などの大豆製品、ナッツ類などの植物性たんぱく質を意識的に摂取しましょう。野菜だけの食事では、必須アミノ酸の一部が不足する可能性もあるため注意してください。高齢者やスポーツをする人は、普段よりも多くのたんぱく質が必要になるため、意識的な摂取が大切です。
体重50kgの人の場合
0.8g × 50kg = 40g のたんぱく質が1日に必要です。
たんぱく質40gは、どれくらいの食事?
以下のようにいろいろな食品を組み合わせることで、自然に摂取可能です。
| 食品 | 量 | たんぱく質量(目安) |
|---|---|---|
| 納豆 | 1パック(45g) | 約7g |
| 卵 | 1個(50g) | 約6g |
| 豆腐 | 1/2丁(150g) | 約10g |
| 牛乳 | コップ1杯(200ml) | 約6g |
| ごはん | 茶碗1杯(150g) | 約4g |
| ブロッコリー | 茹で100g | 約3g |
| 合計 | ― | 約36g(+副菜や間食で40g超えも可) |
たんぱく質「◯g」は、その食品の重さではありません!
たとえば…「豆腐には10gのたんぱく質がある」
→ これは「豆腐の重さが10g」という意味ではなく、豆腐150gの中に、たんぱく質が約10g 含まれているということです。
ポイント
- 動物性・植物性どちらからでもOK。
- 一度にたくさんではなく、3食に分けて少しずつ摂るのがおすすめです。
- スポーツをする人や高齢者は、50g以上必要なこともあります。
長期的にたんぱく質が不足すると、貧血やホルモンバランスの乱れなど、深刻な健康問題につながる場合があります。
重要なビタミンやミネラルが不足する
野菜だけに偏った食事をしていると、ビタミンやミネラルが不足する危険性があります。ビタミンB12は肉や魚、卵、乳製品などの動物性食品に含まれるため、野菜だけの食事ではビタミンB12の摂取量が不十分です。
野菜に含まれる鉄分は「非ヘム鉄」と呼ばれ、動物性食品に含まれる「ヘム鉄」に比べて体への吸収率があまり高くありません。野菜だけを食べていると、鉄欠乏性貧血のリスクが高まるため注意が必要です。野菜だけの食事で不足しやすい栄養素には、カルシウムや必須脂肪酸、亜鉛、ヨウ素、ビタミンDがあります。
カルシウム不足は、免疫力の低下や骨密度の減少、ホルモンバランスの乱れなど、さまざまな健康問題を引き起こします。子どもや妊婦さん、高齢者はたんぱく質不足の影響を受けやすいため、注意してください。バランスの良い食事が大切ですが、動物性食品を摂取したくない場合には、栄養補助食品の利用も選択肢になります。
太る

野菜だけの食事に偏ると、満足感が得られずに間食が増え、総カロリー摂取量が増えて体重増加につながる場合があります。摂取カロリーは、調理法や調味料の使い方によっても変わります。ドレッシングを多く使ったり、野菜を揚げ物や炒め物にしたりすると、カロリーが高くなりがちです。
🥗 サラダはヘルシーでも、ドレッシングでカロリー増!
ドレッシングのカロリー目安(大さじ1あたり)
| 種類 | カロリー |
|---|---|
| フレンチ・サウザン系 | 約70〜90kcal |
| ごまドレッシング | 約80〜100kcal |
| マヨネーズ系 | 約100〜120kcal |
| ノンオイルタイプ | 約10〜30kcal |

大さじ2〜3かければ、それだけでごはん1/2杯分くらいのカロリーになることも!
太りにくくする工夫
- ドレッシングは「少なめ」で、全体によく和える
- レモン汁・酢・ポン酢・ヨーグルトなどをベースに手作りする
- 野菜そのものの味を楽しむ(蒸し野菜・塩揉みなど)
- ナッツやチーズなど、別の味・コクで満足感を出す
すべての野菜が低カロリーというわけではありません。アボカドやじゃがいも、とうもろこしなどは、比較的エネルギーの高い野菜です。特にじゃがいもなどの芋類は分類上は「野菜」ですが、栄養的には主食に近い「でんぷん源」として扱われるため、摂りすぎには注意が必要です。また、市販の野菜ジュースには糖分が多く含まれる傾向があり、飲みすぎるとカロリーオーバーになる可能性もあります。野菜と果物を区別せずに摂っていると、果糖(※2)の過剰摂取につながることがあるため、意識してバランスよく取り入れることが大切です。
果糖は体内で脂肪に変わりやすいため、太る原因です。
※2 果糖とは、果物やはちみつなどに含まれる天然の糖で、強い甘みが特徴です。
酵素の働きを妨げる
一部の生野菜に含まれる成分が酵素の働きを妨げ、栄養素が十分に吸収されなくなるリスクがあります。消化酵素の働きを妨げる可能性がある成分は、以下のとおりです。
- ソラニン(生のジャガイモやナス科野菜)
- トリプシン阻害物質(豆類)
- シュウ酸(ホウレンソウやルバーブ)
- イソチオシアネート(ブロッコリーやキャベツ)
- レクチン(生の豆類)
大量の食物繊維を一度に摂取すると、消化酵素がうまく働かない場合があります。消化酵素の働きを妨げる可能性がある成分を含む野菜は、しっかり加熱することが大切です。
アレルギー反応のリスクがある
野菜にもアレルギーがあります。一般的には果物やナッツのアレルギーがよく知られていますが、特定の野菜にもアレルゲン(アレルギーの原因となる物質)が含まれているため、アレルギー反応を起こすことがあります。
よくある野菜アレルギー
| 野菜 | アレルゲンの例 | 注意点 |
|---|---|---|
| トマト | プロフィリン、リポキシゲナーゼ | 花粉症の人に交差反応があることも |
| セロリ | セロリエキス中のたんぱく質 | 重篤な反応を起こす場合もあり、EUではアレルゲン表示義務あり |
| ニンジン | プロフィリン | 花粉症(特にシラカバ)の人が反応しやすい |
| ピーマン・パプリカ | カプサイシン、プロフィリン | トマトやナスと同じナス科で反応する人も |
| 大豆もやし | 大豆アレルギーの一種 | 大豆アレルギーの人は注意が必要 |
症状の例
- 口の中がかゆくなる(口腔アレルギー症候群)
- 喉がイガイガする
- 皮膚にじんましんが出る
- 重い場合は呼吸困難やアナフィラキシーショック
🥦 野菜アレルギーの割合(推定)
- 全人口の約1〜2%前後にあると考えられています(研究者やアレルギー学会による推定)
- つまり、100人に1〜2人くらいが何らかの野菜アレルギーを持っている可能性があるということです。
これらは、花粉症との「交差反応」でも起きやすく、気が付きにくく見逃されていることも多いです。
🌿 交差反応(こうさはんのう)とは、アレルギーを引き起こす物質(アレルゲン)どうしが「似た形」をしているため、体が別のアレルゲンにも反応してしまうことです。
こんなふうにすれば安心!
- いろいろな野菜をバランスよく食べる(色の違う野菜を意識するとGood)
- 加熱と生を組み合わせる(加熱でかさが減り、食べやすくなり、冷え対策にも)
- よく洗う・皮をむく・ゆでこぼすことで残留物対策
- 体調や体質に合わせて調整する(お腹が弱い人は繊維の多い野菜は控えめに)
「食べすぎが直接アレルギーを引き起こす」とは限らないですが、「食べすぎがアレルギー反応のきっかけになることはある」と考えられています。毎日同じ食べ物を大量に食べるのは避けて、バランスよくローテーションするのがおすすめです。
野菜を食べるメリット
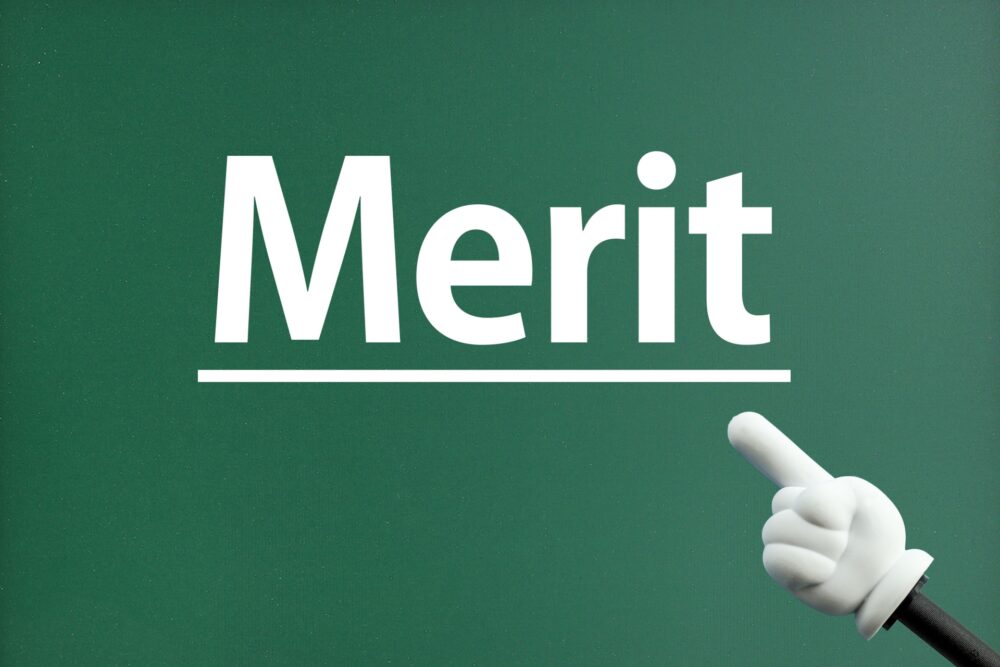
野菜を食べるメリットは、以下のとおりです。
- 健康維持に役立つ
- 消化を助ける
健康維持に役立つ
野菜には、健康維持に役立つ以下の栄養素を含みます。
- 食物繊維
- 食物繊維は腸内環境を整え、便通を改善する効果があります。快適な排便は、体内の老廃物を効率良く排出するために大切です。
- 抗酸化物質
- ビタミンCやビタミンE、ベータカロテンなどの抗酸化物質は、体内の細胞が受ける酸化ストレスを軽減します。
- カリウム
- カリウムは血圧を調整する働きがあり、高血圧の予防につながります。
- 葉酸
- 葉物野菜に含まれる葉酸は細胞の再生を助け、貧血予防に効果的です。
- フィトケミカル
- フィトケミカルは、がんや心臓病などの生活習慣病のリスクを低減する効果があります。
- カロテノイド
- カロテノイドは、加齢による視力低下を予防する効果があります。
- ビタミンK
- ビタミンKは骨の健康維持に貢献し、骨粗しょう症予防に効果的です。
- ミネラル
- マグネシウムやカルシウムなどのミネラルは、筋肉機能や神経伝達をサポートする役割があります。
ダイエット中の人や体重管理が必要な人にとって、野菜中心の食事は理想的です。野菜には免疫力を高める栄養素が豊富に含まれており、風邪やインフルエンザなどの感染症予防にも有効です。
消化を助ける
野菜に含まれる水溶性食物繊維は、腸内で適度な粘性を作り出し、消化吸収をスムーズにします。野菜の繊維質は腸の働きを活発にし、便通改善に効果的です。生野菜に含まれる酵素は消化を助け、アルカリ性の野菜は胃酸を中和して消化器官への負担を軽減します。
野菜に含まれるビタミンB群は、糖質や脂質、たんぱく質の代謝を助けます。野菜に含まれるカリウムは、体内の水分バランスを整えるのに有効です。発酵野菜(キムチやザワークラウトなど)に含まれる乳酸菌も、消化を促進します。消化に不安がある人には、消化吸収しやすい青汁などの野菜ジュースもおすすめです。
野菜の正しい食べ方

野菜を正しく食べるためのポイントは、以下のとおりです。
- バランス良く食事に取り入れる
- さまざまな調理法で楽しむ
- 食前に少量摂取する
- 小分けにして摂取する
- 多様な野菜を取り入れる
バランス良く食事に取り入れる
野菜をバランス良く取り入れるために、以下の方法を実践しましょう。
- 主食・主菜・副菜を組み合わせる
- 適量の油と組み合わせる
- 生野菜と加熱野菜の両方を取り入れる
- 季節の野菜を取り入れる
- 野菜と穀物のバランスを考慮する
個人の体質や健康状態に合わせて、野菜の種類や量を調整してください。
» 長期的な健康を目指す!栄養バランスを整える方法と献立作りのコツ
さまざまな調理法で楽しむ

野菜を調理する方法により、栄養素の吸収率や味わいが変わります。生で食べるサラダは、水溶性ビタミンをそのまま摂取できる点がメリットです。茹でる・蒸す・焼く・炒める・煮るなどの加熱調理をすると、食物繊維が柔らかくなり、消化吸収がしやすくなります。
油を使った調理では、ビタミンA・D・E・Kなどの脂溶性ビタミンの吸収率が向上します。発酵は保存性が高まるだけでなく、栄養価も向上させる調理法です。夏は冷製サラダや冷やし野菜、冬は温かいスープや煮物など、季節感を取り入れると、飽きずに野菜を食べられます。
切り方や下茹での工夫により、食べやすさや調理時間の調整が可能です。複数の野菜を組み合わせれば、栄養バランスも向上します。野菜の苦みが気になる人は、調味料や香辛料を活用するのがおすすめです。野菜をスムージーやジュースにすれば、忙しい人でも手軽に摂取できます。
食前に少量摂取する
食前に野菜を食べると、血糖値の急上昇を抑えられます。血糖値が気になる人や体重管理をしたい人にとって、大きなメリットです。食物繊維が先に胃に入ることで満腹感が得られるため、全体の食事量を自然に減らせます。食事の15〜30分前に摂取すると、食べ過ぎ防止に効果的です。
生野菜なら100g程度、加熱野菜なら50〜70g程度を目安にしましょう。野菜を先に食べると、消化酵素の分泌も促進されます。サラダを食べる際には、油分控えめのドレッシングを選びましょう。水分補給と食欲コントロールには、野菜スープが効果的です。よく噛むことで満腹中枢が刺激され、食べ過ぎを防げます。
小分けにして摂取する

野菜の1日の必要量を複数回に分けて食べると、体への負担を減らしながら栄養素をしっかり吸収できます。小分けにして野菜を摂取する際には、以下の配分がおすすめです。
- 朝食:30〜50g
- 昼食:100〜150g
- 夕食:150〜200g
間食には、野菜スティックやスムージーを活用しましょう。野菜サラダを前菜と主菜の間に分けて食べる方法も、満腹感のコントロールに効果的です。
多様な野菜を取り入れる
色とりどりの野菜を選ぶことで、さまざまな種類の栄養素を効率的に摂取できます。各色の野菜に含まれる栄養素は、以下のとおりです。
- 緑色の野菜:葉酸やビタミンK
- 赤色の野菜:リコピン
- 黄色の野菜:βカロテン
- 白色の野菜:アリシンなどの機能性成分
- 紫色の野菜:アントシアニン
旬の野菜や地元の野菜を選ぶことも大切です。旬の野菜は栄養価が高く、価格も比較的リーズナブルです。忙しい人は、冷凍野菜を活用しましょう。冷凍野菜は収穫後すぐに加工されるため、栄養価が高く保たれています。苦手な野菜がある場合は、小さく刻んだり、味付けを工夫したりしましょう。
普段食べない野菜を週に1つ試してみると、食のバリエーションが広がります。根菜類や葉物野菜、果菜類をバランスよく組み合わせることも重要です。
野菜を食べ過ぎるデメリットに関するよくある質問
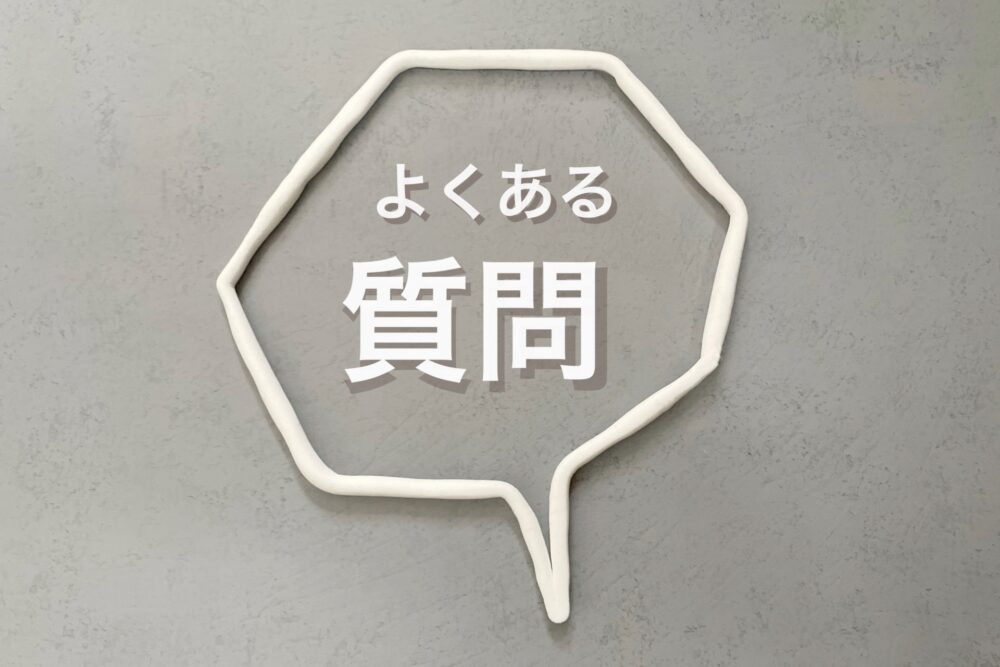
野菜を食べ過ぎるデメリットに関してよくある質問は、以下のとおりです。
- 野菜はどのくらいの量から食べ過ぎになる?
- 野菜ジュースは野菜の代わりになる?
野菜はどのくらいの量から食べ過ぎになる?
野菜を1日500〜600g以上食べると、過剰摂取になる可能性があるため注意が必要です。生野菜は300〜400g以上で消化に負担がかかる可能性があります。高繊維質の野菜(キャベツやブロッコリーなど)は、200〜300g以上で過剰摂取といわれています。
根菜類は糖質が多いため、1日200g程度を目安にしましょう。葉物野菜は比較的多く摂取しても問題ありませんが、400g以上摂取すると消化器系に負担がかかります。食物繊維の過剰摂取(1日25g以上)は腸に負担をかける可能性があるため注意してください。
体質や健康状態によって適量は異なるため、体調不良や消化器系の問題がある場合は、医師や栄養士に相談しましょう。
野菜ジュースは野菜の代わりになる?
野菜ジュースは、完全には野菜の代わりになりません。野菜ジュースは生の野菜と比較すると、栄養素や食物繊維が減少します。加工過程で水溶性ビタミン(ビタミンCなど)が失われやすい傾向にあります。市販の野菜ジュースに含まれる添加物や砂糖にも、注意が必要です。
野菜をそのまま食べることで、咀嚼による満腹感や消化酵素の分泌が促されるほか、食感を楽しめるメリットもあります。野菜摂取が不足している場合には、野菜ジュースを補助的な役割として活用しましょう。無添加・低糖質の野菜ジュースがおすすめです。自宅で野菜ジュースを作れば、栄養素の損失を最小限に抑えられます。
まとめ

野菜は健康維持に重要な食材ですが、食べ過ぎには注意が必要です。厚生労働省が推奨する1日の野菜摂取量は、350gです。350gを大幅に超えると、下痢や便秘などの消化器系トラブルを引き起こす可能性があります。野菜の摂り過ぎは、胃痛や吐き気、重要栄養素の不足、過剰な糖質摂取につながる場合もあります。
健康維持のためには、バランス良く多様な野菜を少量ずつ取り入れましょう。野菜の調理法を工夫したり食事の前に少量ずつ食べたりすることで、効果的に野菜を摂取できます。野菜だけに偏らず、さまざまな食品をバランス良く摂取することも重要です。