
毎日の献立作りに悩む方は多くいます。忙しい方にとって、栄養バランスを考えた献立作りは大変です。この記事では、主菜の定義や種類、栄養素、調理法について詳しく解説します。記事を読むと、主菜の理解が深まり、バランスの取れた食事作りに役立ちます。
主菜は食事の中心となるおかずで、タンパク質源となる食材を使用する点が特徴です。主菜を上手に選び、栄養バランスの良い食事を作りましょう。
» 食生活の重要性と年齢別の改善方法を解説
主菜とは献立のメインとなるおかず

主菜は食事の中心となり、栄養バランスを整える役割を果たします。タンパク質源を含む料理が多く、肉や魚、卵、大豆製品などが主な材料です。メインディッシュとして、量が多くボリュームがあります。家族の好みや季節、地域性を考慮して、栄養バランスを考えて選びましょう。
» 長期的な健康を目指す!栄養バランスを整える方法と献立作りのコツ
主菜の種類

主菜の種類を以下のカテゴリーに分けて解説します。
- 肉を使った主菜
- 魚を使った主菜
- 大豆製品を使った主菜
- 野菜を使った主菜
肉を使った主菜
肉を使った主菜は、タンパク質が豊富です。エネルギー源として優れています。肉を使った主菜は、ステーキやハンバーグ、焼肉、唐揚げ、とんかつなどです。調理法によって異なる食感や風味を楽しめます。肉料理は栄養価が高いだけでなく、満足感も得られるため、共働き夫婦や一人暮らしの方にもおすすめです。
カロリーが高めなため、ダイエット中や食事制限のある方は摂取量に注意しましょう。肉じゃがやカレーなど、野菜と組み合わせると、栄養バランスを整えられます。高齢の方は、消化しやすい調理法を選んだり、脂肪分を控えめにしたりするなどの工夫をしましょう。
魚を使った主菜
魚を使った主菜は、良質なタンパク質や健康的な脂質を含み、さまざまな調理法でおいしく楽しめます。代表的な魚料理は、以下のとおりです。
- 焼き魚
- 煮魚
- 刺身
- 魚のフライ
- 魚の照り焼き
洋風料理では魚のムニエルやカルパッチョ、中華風では魚の酢豚風などがおすすめです。魚料理は調理法によって味わいが大きく変わるため、家族の好みに合わせて選びましょう。魚を主菜に選ぶと、健康的でバラエティ豊かな食生活を送れます。
大豆製品を使った主菜

大豆製品を使った主菜は栄養価が高く、ヘルシーです。豆腐や油揚げ、高野豆腐などを使った料理はタンパク質が豊富で、さまざまな調理法で楽しめます。
代表的な大豆製品を使った主菜は、以下のとおりです。
- 豆腐ステーキ
- 麻婆豆腐
- 肉詰め油揚げ
- 高野豆腐の含め煮
- 厚揚げの照り焼き
- 豆腐ハンバーグ
大豆製品の使用量とカロリー比較
| 料理 | 大豆製品 | 大豆製品の使用量 | 使用大豆製品のカロリー | 料理全体のカロリー |
|---|---|---|---|---|
| 豆腐ステーキ | 木綿豆腐 | 150g | 108.0 | 173.4 |
| 麻婆豆腐 | 木綿豆腐 | 150g | 108.0 | 316.05 |
| 肉詰め油揚げ | 油揚げ | 50g | 193.0 | 419.0 |
| 高野豆腐の含め煮 | 高野豆腐 | 20g | 104.6 | 143.6 |
| 厚揚げの照り焼き | 厚揚げ | 100g | 150.0 | 215.4 |
| 豆腐ハンバーグ | 木綿豆腐 | 100g | 72.0 | 280.6 |
肉や魚の代替として使えるため、ベジタリアンの方や動物性タンパク質を控えたい方にもおすすめです。大豆製品は他の食材とも相性が良く、野菜や肉、魚と組み合わせると、栄養バランスの取れた主菜を作れます。低カロリーでありながら満足感があるため、ダイエット中の方や食事制限がある方にも最適です。
上の表のように、調理法や味付けによっては、カロリーが高くなる場合もある点に注意しましょう。
野菜を使った主菜
野菜を主役にすると、ヘルシーでおいしい料理を楽しめます。代表的な野菜を使った主菜には、ラタトゥイユや野菜のグラタン、野菜の肉巻きや野菜のキッシュなどがあります。野菜の持つ栄養価を最大限に生かしつつ、満足感のある一品に仕上げることが可能です。
野菜を主菜にする際に気を付けること
① 野菜の栄養を損なわないよう、茹ですぎない。ゆで水にビタミン類が出てしまいます。蒸す、炒めるは、それは少なくなりますが、炒める場合は油の量は控えめに。
② 野菜だけだと味が薄くなりやすいので、スパイスやハーブ、調味料などで工夫しましょう。
③ 柔らかい野菜と歯ごたえのある野菜を組み合わせると、食感を楽しめ、食べやすくなります。
野菜を主菜にすると、低カロリーでありながら食物繊維やビタミン、ミネラルを効率よく摂取できます。ダイエット中の方や健康に気を使っている方にとって、理想的な選択肢です。野菜の持つ自然な甘みや旨味を引き出すと、肉や魚を使わなくてもおいしい主菜を作れます。
色とりどりの野菜を組み合わせると、見た目も美しく栄養バランスの良い料理ができます。
主菜に含まれる栄養素

主菜に含まれる栄養素は、以下のとおりです。
- タンパク質
- ビタミン・ミネラル
- 脂質
タンパク質
タンパク質は体の構成要素として、さまざまな役割を果たします。タンパク質の主な働きは、以下のとおりです。
- 筋肉・皮膚・髪・爪などの組織を作る
- 酵素やホルモンの原料となる
- 免疫機能の維持に必要となる
- エネルギー源としても利用できる
1日の推奨摂取量は、体重1kg当たり約1gです。タンパク質は動物性と植物性に分けられ、肉や魚、卵、大豆製品などに多く含まれています。必須アミノ酸を含む完全タンパク質が理想的です。タンパク質は消化吸収に時間がかかるため、満腹感が持続します。
ダイエット中の方や高齢の方にも適していますが、過剰摂取は腎臓に負担をかける可能性があるため、注意しましょう。
ビタミン・ミネラル
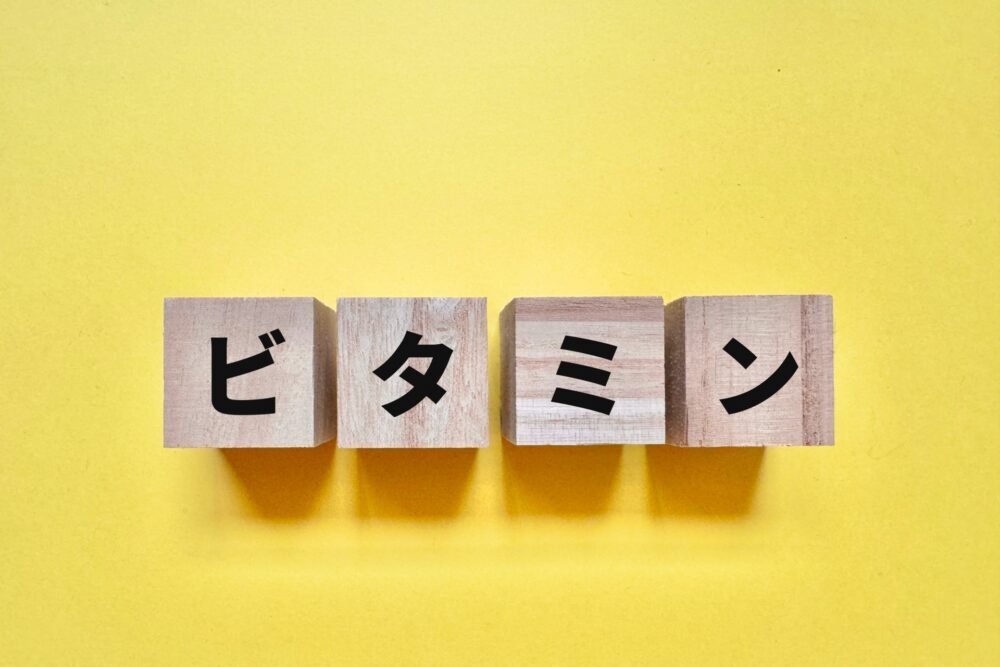
ビタミンとミネラルは、体のさまざまな機能を支える役割を果たします。ビタミンAは視力維持や皮膚の健康に役立ち、ビタミンB群はエネルギー代謝や神経機能をサポートします。ビタミンCは免疫機能を強化し、抗酸化作用があるのが特徴です。鉄は赤血球の形成に不可欠で、カルシウムは骨や歯の健康を維持します。
亜鉛は免疫機能や味覚に関与します。主菜だけでなく、副菜や果物などからもバランスよく摂取することが大切です。ビタミンやミネラルは体内で合成できないものが多いため、日々の食事から意識的に摂取しましょう。
ビタミンを効率よく摂るための食品&調理法比較表
| ビタミン | 種類 | 多く含む食品 | 吸収を良くする調理のコツ | おすすめの調理例 |
|---|---|---|---|---|
| ビタミンB1 | 水溶性 | 豚肉、玄米、豆類、うなぎ | 短時間で加熱し、煮汁ごと食べる | 豚汁、スープ、豆の煮物 |
| ビタミンB2 | 水溶性 | レバー、卵、乳製品、納豆 | 汁ごと摂取か、炒めたり焼いたりする | レバニラ炒め、卵焼き、納豆ご飯 |
| ビタミンC | 水溶性 | レモン、オレンジ、キウイ、ピーマン、ブロッコリー | 生または短時間で加熱する | サラダ、スムージー、レンジ蒸し野菜 |
| ビタミンA | 脂溶性 | にんじん、レバー、かぼちゃ、ほうれん草 | 油と一緒に調理する | にんじんのきんぴら、ほうれん草ソテー |
| ビタミンD | 脂溶性 | 鮭、卵黄、干ししいたけ、きのこ類 | 油脂と一緒に調理する | 鮭のムニエル、きのこソテー |
| ビタミンE | 脂溶性 | アーモンド、ナッツ類、アボカド、植物油 | 加熱しすぎず、生または軽く調理する | ナッツサラダ、アボカドトースト、ドレッシング |
| ビタミンK | 脂溶性 | 納豆、小松菜、ほうれん草、ブロッコリー | 油を使って短時間調理する | 小松菜炒め、納豆チャーハン |
脂質
脂質はエネルギー源として体を動かすのに役立ちます。体温を保ち、臓器を守る役割もあります。脂質は、動物性脂質と植物性脂質に分けられるのが特徴です。動物性脂質は肉や魚に多く含まれていますが、過剰摂取は体に悪影響を与える可能性があります。植物性脂質は大豆製品や野菜に含まれており、体に良い影響を与えます。
植物性油脂にも、体に良いものとそうでないものがあります
①植物性油脂のなかでも体に良いもの
・オリーブオイル(エクストラバージンオイル):抗酸化作用があり、心臓病や動脈硬化のリスクを下げると言われています。
・アボカド、ナッツ類(アーモンドやクルミなど):栄養価が高く、良質な脂肪やビタミンが含まれています。
・エゴマ油、亜麻仁油:オメガ3脂肪酸が豊富で、炎症を抑える効果が期待できます。
これらの油脂は、不飽和脂肪酸や抗酸化物質が豊富で、健康効果が科学的にも示されています。
②植物性でも注意したい油脂(体に悪いとされるもの)
- マーガリンやショートニング:加工過程で人工的に作られた「トランス脂肪酸」が含まれることがあります。トランス脂肪酸は心臓病や動脈硬化のリスクを高めると言われ、摂取を控えた方がよいとされています。
- 植物性ホイップクリーム(安価なもの):添加物や加工油脂が多く使われ、自然な食品とは言えません。健康のためには避けるか、頻度を減らすことが望ましいです。
- 精製度が高く、酸化しやすい油脂(安価なサラダ油や古くなった植物油):これらは酸化しやすく、体内での炎症を起こす可能性があります。

「植物性か動物性か」だけではなく、「人工的に加工されているかどうか」も、健康を考える上でとても大切なポイントになります。
適切な脂質の摂取量は、1日の総エネルギーの20〜30%程度です。脂質は必須脂肪酸の供給や、脂溶性ビタミンの吸収を助ける役割も果たします。細胞膜の構成成分になる点も特徴です。トランス脂肪酸の摂取には、注意しましょう。
» 脂質の1日の必要量は?男女別、ライフスタイル別に解説
主菜の調理法

主菜の調理法は以下のとおりです。
- 焼く
- 煮る
- 揚げる
- 蒸す
焼く
焼く調理法は、高温で素早く調理できるため、忙しい方や一人暮らしの方に適しています。焼く調理法の特徴は、以下のとおりです。
- 食材の表面を香ばしく仕上げられる
- 余分な脂を落とせる
- 調理時間が短く栄養素の損失を減らせる
魚や肉、野菜など幅広い食材に適用できるため、家族や高齢の方にも簡単においしい料理を作れます。ダイエット中や食事制限がある方にとっても、焼く調理法は優れた選択肢です。余分な脂を落とせるため、カロリーを抑えつつ、食材本来の旨味を楽しめます。焼き過ぎには注意が必要です。そして、焼く際に、油をたっぷり使ってしまっては、カロリーがあがってしまいます。
おすすめの焼き方
- 油は薄く塗るだけにする。
- ノンスティック(くっつかない)調理器具や、オーブンシートを使う。
- オーブンや魚焼きグリルなどで、脂を下に落として焼く。
- 野菜を一緒に焼いて栄養バランスを整える。
肉や魚と一緒に脂溶性ビタミンの野菜を焼くと、調理の油を使わなくてすみ、ビタミンの摂取が効率よくなる。野菜の食物繊維が食事の脂肪を吸収し、消化吸収をゆるやかする。
煮る
煮る調理法は、食材の旨味を逃がさず栄養素を保持できるため、健康的な料理を作るのに適しています。煮る調理法の特徴は、以下のとおりです。
- 食材が柔らかく仕上がる
- 消化しやすい
- 調味料が食材に浸透しやすい
- 味わい深くなる
煮込み料理やシチュー、スープなどにも応用でき、レパートリーが広がります。煮汁の量や火加減を調整するのがポイントです。一度に大量調理が可能なため、経済的な点も魅力です。共働き夫婦や一人暮らしの方にとっては、時間を節約できる調理法として重宝します。
ダイエット中や食事制限がある方にも、栄養素を逃がさず調理が可能です。
揚げる

揚げる調理法は、カラッとした食感と香ばしさが特徴です。衣をつけることで油の浸透を防ぎ、中身をジューシーに保てます。天ぷらやフライ、唐揚げなどさまざまな料理に応用でき、油の選択で風味を変えられるのも特徴です。揚げ物は高カロリーになりやすいため注意しましょう。余分な油を切ると、カロリーを抑えられます。
食材を揚げる際は、揚げ時間と温度管理が重要です。
食材別・揚げる温度と時間・注意点 比較表』(揚げ時間・温度管理入り)
| 食材の種類 | 食材の例 | 油の温度(目安) | 揚げ時間(目安) | 気をつけるポイント・調理方法 |
|---|---|---|---|---|
| 肉類 | とんかつ、から揚げ | 170~180℃(中~高温) | 3~5分 | 肉の厚みによって調整。衣がきつね色になれば完成。 |
| 魚介類 | エビフライ、白身魚、牡蠣フライ | 170~180℃(中~高温) | 2~4分(牡蠣は3~4分) | 身が崩れやすいため、衣が固まるまで触らない。牡蠣は特に水気を切り厚めの衣で揚げる。 |
| 芋類・野菜・加工品 | コロッケ、ポテトフライ、茄子、ピーマン | 170~180℃(中~高温) | 3~4分 | 衣がサクッとなるまで触りすぎずに揚げる。 |
| 根菜類 | じゃがいも、さつまいも、かぼちゃ | 160~170℃(低~中温) | 5~7分 | 中心まで火が通ったか竹串などで確認。 |
| 葉野菜 | 大葉、春菊、パセリ | 170~180℃(中~高温) | 数秒~20秒程度 | 焦げやすいので短時間でさっと揚げる。水気はよく切る。 |
| 山菜類(山菜天ぷら) | ふきのとう、タラの芽、こごみ | 170~180℃(中~高温) | 1~2分 | 揚げすぎると苦味が出るので短時間。水気はよく切る。 |
| 豆腐類 | 厚揚げ、揚げ出し豆腐 | 170~180℃(中~高温) | 2~3分 | 水気を切り、油ハネに注意。表面がきつね色になれば完成。 |
| 練り製品 | かまぼこ、ちくわの天ぷら | 170~180℃(中~高温) | 2~3分 | 衣を薄めにして短時間でさっと揚げる。 |
| 冷凍食品 | コロッケ、から揚げ、カニクリームコロッケ | パッケージの指示に従う(約160~170℃) | パッケージの指示に従う(約5~7分) | パッケージに「加熱済み」または「生(未加熱)」の表記があるか注意。 |
蒸す
蒸し料理は蒸し器や電子レンジを使って、食材の水分と栄養を逃がさずに調理ができます。低カロリーかつヘルシーである点や、食材本来の味を生かせるのが魅力です。加熱しすぎる心配が少なく、柔らかく仕上がり、調理時間が短いのも特徴です。魚や野菜を蒸すと、素材の風味を損なわずに仕上げられます。
油を使わないため、ダイエット中の方や食事制限がある方にもおすすめです。複数の食材を同時に調理でき、忙しい方や一人暮らしの方にも便利です。

蒸篭(せいろ)での蒸し料理は、違う食材も一度に盛り合わせて蒸すことができます。一人一枚の蒸篭でそのまま食卓に出すスタイルは特別感があり、料理も熱々で、今後さらに流行する可能性があります。
主菜の選び方

主菜の選び方は、以下を参考にしてください。
- 季節
- 地域
- 家族の好み
- カロリー
季節
旬の食材を使うと栄養価が高く、おいしい料理を作れます。春は新鮮な野菜や山菜、桜鯛などの旬の魚を使った料理がおすすめです。栄養が豊富で、体を目覚めさせるのに適しています。夏はさっぱりした冷たい料理や、冷やし中華、そうめん、などが人気です。
暑い季節は食中毒のリスクが高まるため、冷たい料理や火をしっかり通した料理を選びましょう。秋はきのこ類やさんま、栗、さつまいもなどの食材が旬を迎えます。栄養価が高く、体を冬に向けて準備するのに役立ちます。冬は鍋料理やおでん、温かい煮込み料理がおすすめです。
季節感のある料理で食卓を彩ると、日々の食事がより楽しくなります。
地域
主菜の選び方において、地域性を考慮することは大切です。地域ならではの食材や調理法を取り入れると、より豊かな食卓を作れます。地域の特産品や郷土料理を活用しましょう。地元の新鮮な食材を選ぶと、おいしく栄養価の高い主菜を作れます。地域の気候や風土に合わせた料理を選択すると、体調管理にも役立ちます。
地元の生産者との連携や、地域の食育活動を活用するのも良い方法です。
最近の具体的な活用方法
① 産直型オンラインマルシェ
② SNS・ライブ配信を活用した生産者との交流
③ 地域型サブスクリプション(定期便)
④ 地域コラボのミールキット
⑤ コミュニティキッチン・地域食堂
⑥ 地域×シェフのコラボイベント
こうした新しい方法を取り入れることで、地域の食材や食文化がより広く知られ、地域活性化や食育にも大きな効果があります。
家族の好み

主菜を選ぶ際は家族の年齢層や健康状態、好みの味付けや調理法を考慮しましょう。アレルギーや食事制限、子どもの嗜好や苦手な食材を把握し、工夫して取り入れてください。家族の食文化や伝統的な料理の好みを反映させましょう。新しい食材や料理にチャレンジするのもおすすめです。
適量を心がけると、食品ロス削減にもつながります。家族の健康目標や栄養バランスを意識した選択を心がけましょう。
» 食事の適量を年齢やライフスタイル、栄養素別に解説
カロリー
主菜のカロリーは、食材や調理法によって大きく変わります。1食の主菜のカロリー目安は、300〜500kcal程度です。ダイエット中の方は、200〜300kcal程度に抑えましょう。
カロリーを抑えるコツは、以下のとおりです。
- 油を控える
- 蒸す・焼くなどの調理法で調理する
- 野菜を多く使う
カロリー表示のある冷凍食品や惣菜を活用するのも、カロリー管理の助けになります。カロリーだけでなく、栄養バランスも考慮しましょう。高齢者や食事制限がある方は、個々の状況に応じてカロリー調整が必要です。
主菜に関するよくある質問

主菜に関するよくある質問は、以下のとおりです。
- 主菜と副菜の違いは?
- 主菜は必ず肉や魚でなければならない?
- 主菜だけで栄養は十分?
主菜と副菜の違いは?
主菜は献立の中心となる料理で、タンパク質や脂質を多く含みます。副菜は主菜を補完し、ビタミンやミネラルを提供する役割があります。主菜は量が多く、副菜は比較的少量です。主菜は肉や魚、卵や大豆製品などが中心となり、副菜は野菜やきのこ、海藻類などが中心です。
主菜はエネルギー量が高く、副菜は低めの傾向があります。主菜は1品、副菜は複数用意される場合が多くあります。
» 1週間の献立の立て方と効率的な食事プランのコツを紹介!
主菜は必ず肉や魚でなければならない?

主菜は必ずしも肉や魚を使う必要はありません。植物性のタンパク質源を使った主菜も、十分に栄養価が高いのが特徴です。大豆製品や野菜を使った主菜も、十分なタンパク質を含んでいます。個人の食生活や健康状態に応じて、主菜の選択肢は広がります。
ベジタリアンやヴィーガンの方は植物性タンパク質を中心とした主菜で、必要な栄養の摂取が可能です。多様な食材を使うと、栄養バランスを整えられます。肉や魚以外の主菜を選ぶと、環境への負荷を減らせます。食事の選択は個人の自由であり、健康的な食生活を送るための方法は1つではありません。
主菜だけで栄養は十分?
主菜だけでは、十分な栄養を摂取するのは困難です。栄養価は高いものの、栄養バランスが偏る可能性があります。タンパク質や脂質は主菜から十分に摂取できますが、炭水化物や食物繊維が不足しがちです。ビタミンやミネラルの種類も限られます。栄養バランスを改善するには、副菜や汁物を組み合わせるのが効果的です。
主菜の種類や調理法を工夫すると、より多くの栄養素を摂取できます。野菜を使った主菜を選んだり、蒸し料理にしたりするのも良い方法です。個人の健康状態や目的によっては、主菜の量や種類を調整する必要があります。主菜だけでなく、バランスの取れた食事を心がけてください。
まとめ

主菜はタンパク質やビタミン、ミネラルなどの必須栄養素を豊富に含み、健康的な食生活の基礎となります。肉や魚、大豆製品、野菜など、多様な食材を使って主菜を作れば飽きずに続けられます。焼く、煮る、揚げるなどさまざまな調理法を活用し、同じ食材でも異なる味わいを楽しみましょう。
季節や地域性、家族の好みやカロリーなどを考慮して主菜を選ぶと、より満足度の高い食事を作れます。主菜と副菜のバランスを意識することが重要です。多様な主菜を取り入れて副菜と組み合わせれば、栄養バランスの良い食事を作れます。